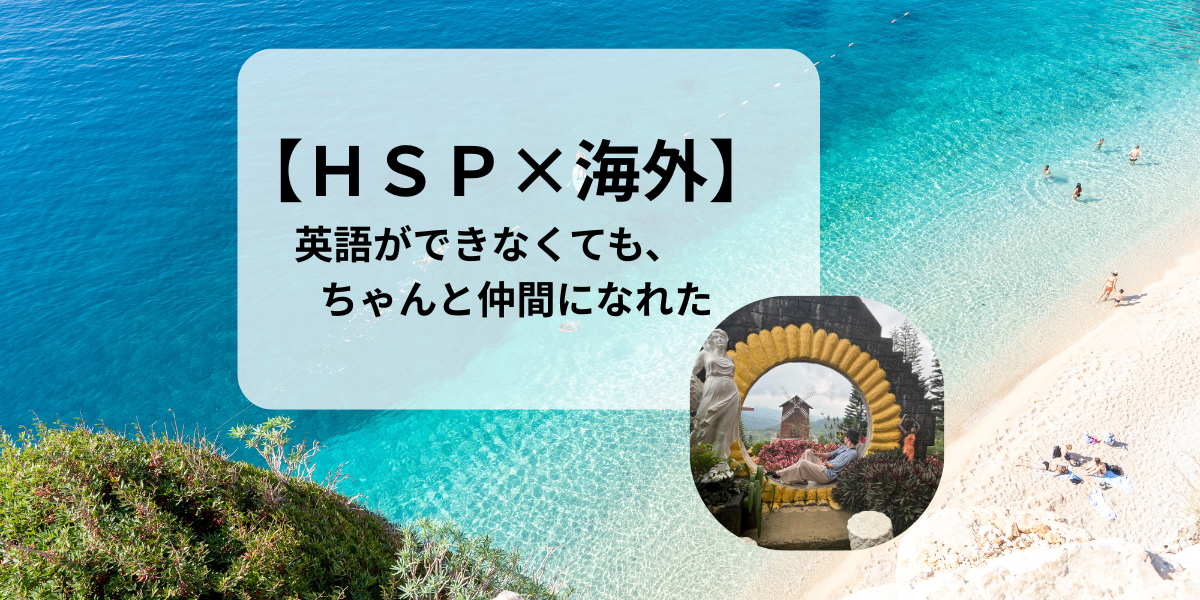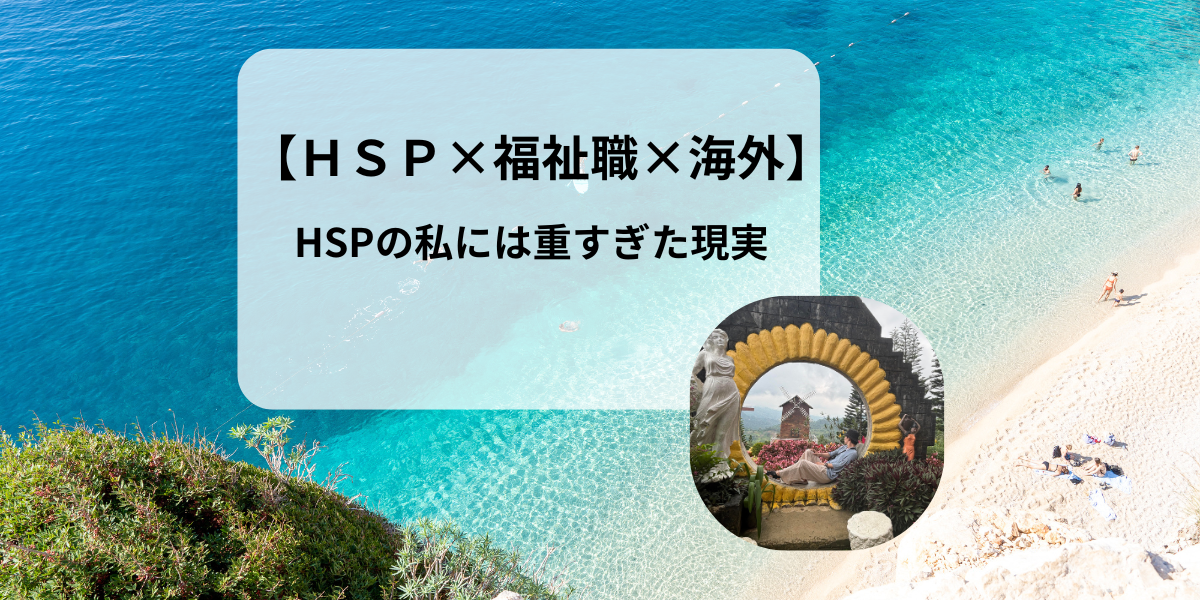児童自立支援施設とは?役割と現場のリアル

児童自立支援施設とは?
児童自立支援施設とは、不良行為をした、またはそのおそれのある子どもを対象に、自立に向けた生活指導や学習支援を行う児童福祉施設です。
児童福祉法44条に基づき設置されており、子どもたちが社会の中で健やかに生きていく力を身につけられるように支援する場でもあります。
「少年院」と混同されがちですが、児童自立支援施設は刑罰を与える場ではなく、あくまで福祉的な支援を目的としています。
児童自立支援施設の主な役割
児童自立支援施設では、子どもたちの心身の成長と社会的自立を目指して、次のような役割を担っています。
- 子どもの生活全般の支援(規則正しい生活・集団生活の指導)
- 学習支援(学校教育との連携や施設内での授業)
- 職業体験や社会参加活動の提供
- 心理的ケアやカウンセリング
- 保護者や家庭への支援・連携
「子どもを罰する場」ではなく、「子どもの成長を支える学びと生活の場」であることが大きな特徴です。
児童自立支援施設での生活と支援内容
児童自立支援施設の子どもたちは、日々の生活を通じて「社会で自立していく力」を身につけていきます。
規則正しい生活
毎日の起床・食事・就寝といった基本的な生活リズムを整え、集団生活の中で協調性や責任感を学びます。
学習支援
施設内に設置された学校(分校)や、地域の学校と連携して学習を続けられるようにサポートします。
学力の遅れを取り戻す取り組みも重要な役割です。
職業体験
農業、調理、清掃などの作業体験を通じて、働くことの意味や社会参加の意義を実感できる機会を提供します。
心理的支援
子どもたちの多くは家庭環境や人間関係に課題を抱えています。
心理士や職員による面談、グループワークなどを通じて、自己理解や感情調整を学びます。
児童自立支援施設での日常と子どもたちの姿
私は大学卒業後に福祉職の公務員となり、児童自立支援施設に三年間勤務しました。
初めて入所している子どもたちのケース記録を読んだ時、衝撃を受けたことをよく覚えています。
普通に生活していたら想像もできないような経験をしてきた子どもたちばかりだったのです。
最初はそんな子どもたちと生活していくことがとても怖かったですね。
それぞれが大きな問題を抱えている子どもたちが一つの施設で生活を共にするため、トラブルは絶えません。
私が働いていた頃は中学生が多かったですが、テレビの順番や誰がおもちゃを使うかなど、些細なことで大きな喧嘩に発展していました。
そのため、生活のルールは非常に細かく設定されていましたね。
何かしらの問題行動をしてきた子たちが集まっていますが、まだまだ子どもです。
不穏になり大暴れするようなこともありますが、時には無邪気に遊んだり笑ったりしている姿も見せてくれます。可愛らしいなと思うことも多かったです。
仕事に慣れていた頃には、子どもたちとの生活への恐怖心はほとんどなくなり、成長を見守りたい気持ちの方が大きくなっていました。
児童自立支援施設の仕事の現実と退所後の課題
施設で勤務した三年間で、様々な児童の退所を見届けてきました。
退所後の生活はどうか上手くいってほしいと願って送り出すのですが、残念ながらまた同じような失敗を繰り返してしまう子が多いです。
先輩に聞いたところ、退所後に上手くいく子の方が少ないと言っていました
施設で頑張っている姿を見てきた分、ショックは大きかったです。
人は簡単には変わらない、現実は厳しいと痛感しました。
私の想像では、児童自立支援施設に入所している子はいわゆる非行少年のような子が多いのかなと思っていました。
昔はそうだったらしいのですが、今はそういった子は少ないです。
何かしらの障害等抱えている子やSNS等の影響で非行に走ってしまった子が多いように感じました。
時代が変われば入所してくる子たちの傾向も変わる。
児童対応についても日々模索し、変化しなければいけないのだと思います。
👉 「関連記事:児童自立支援施設で出会った『気持ちが分からない』子どもの成長物語」

まとめ:児童自立支援施設は「子どもの未来を支える場所」
児童自立支援施設とは、問題行動のある子どもを罰する場所ではなく、生活支援・学習支援・心理的ケアを通して社会的自立を支える児童福祉施設です。
問題を抱えた子どもを単に矯正する場ではなく、彼らの成長と自立を支援する「居場所」なのです。
生活指導や学習、職業体験、心理的支援を通じて、再び社会の中で前向きに生きていける力を育む役割を担っています。
ときには厳しい指導が必要になる場面もありますが、その根底にあるのは「子どもの未来を信じて支える」という思いです。
児童自立支援施設は、社会にとっても子どもの未来を支える大切な存在なのです。
この記事が、児童自立支援施設の役割や現場のリアルを知るきっかけになれば幸いです。
🌱 福祉職を目指す方やHSPの方にとっても、「子どもと向き合う現場」の理解は大きな学びになります。
👉 他の記事では、児童相談所やHSPと福祉職のリアルについても紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。