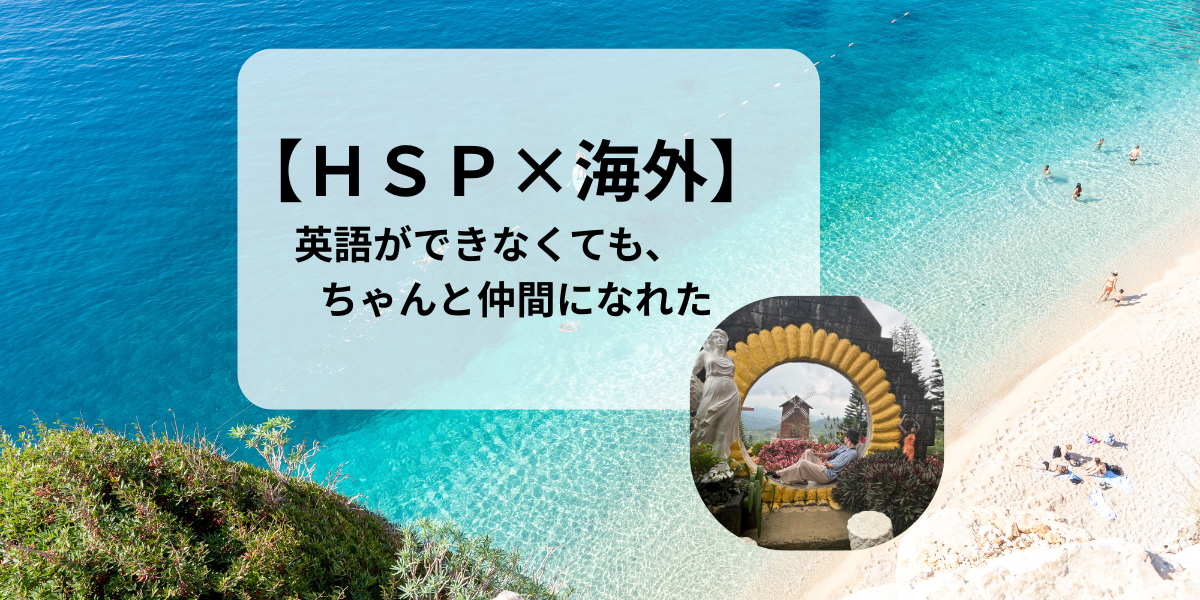児童相談所とは?役割と現場で働く人の実際

児童相談所とは?
児童相談所(通称:児相)は、子どもに関するあらゆる相談を受け付け、支援や保護を行う行政機関です。
虐待対応のイメージが強いですが、それだけでなく、発達や養育、非行など幅広い分野を扱います。
児童福祉法に基づき設置され、都道府県や政令指定都市に最低1つは存在しています。
社会的に弱い立場にある子どもを守り、健やかな成長を支えるための重要な役割を担っています。
児童相談所の主な役割
児童相談所は、子どもと家庭を包括的に支えるために、次のような役割を担っています。
- 子どもに関する相談対応(虐待・発達・家庭問題・非行など)
- 必要に応じた調査や心理検査
- 保護者への支援や指導
- 一時保護や施設・里親への委託
- 関係機関(学校・医療・警察など)との連携
「子ども本人だけでなく、家庭や地域を含めた環境全体をどう支えていくか」が大切な視点になります。
児童相談所の仕事内容・業務内容
業務は多岐にわたり、職員は専門的な知識と調整力を求められます。
相談・調査対応
電話や来所での相談を受け付け、必要に応じて家庭訪問や面接を行います。
虐待の有無や生活状況を把握し、支援方針を検討します。
一時保護
子どもの安全が確保できない場合には、一時保護所で生活を守ります。
保護の判断は迅速さが求められ、心理的にも大きな負担が伴う部分です。
保護者支援
「子どもを守る=親を排除する」ではなく、可能な限り家庭での養育を支える姿勢が基本です。
保護者への助言・指導、生活支援につなげることも重要な仕事です。
関係機関連携
学校、病院、福祉機関、警察、裁判所など、多職種・多機関との連携が欠かせません。
調整役としての役割も大きなポイントです。
児童相談所の仕事の大変さと現場のリアル
大学卒業後に福祉職の公務員になった私は、三年間児童自立支援施設で働いた後、四年目に児童相談所へ配属となりました。
担当業務は主に虐待の初期対応でした。
親への指導や子どもの保護等、かなり大変な業務を行っていました。
保護者から罵声を浴びせられることや子どもの泣き叫ぶ姿を見ることは日常茶飯事です。
一時保護を行うようなケースでは、ひどい虐待を受けていることも多いです。
子どもを守るためにも、やむを得ず保護をすることもよくあります。
とはいえ、突然知らない施設へ保護されることの精神的負担は計り知れません。
これが最善の対応だったのか、もっと早く介入できなかったか、今後子どものために何ができるかなど、悩みや葛藤は尽きません。
👉 「関連記事:HSP社会福祉士が体験した、虐待対応で心が限界に達した日」

今だから言える、児童相談所で学んだこと
福祉職に就いてから、普通に生活していたら知ることのなかった信じられないケースをたくさん目にしてきました。
仕事を通じて、世の中にはこんなにも苦しんでいる大人や子どもたちがいること、当たり前と思っていた生活がどれだけ幸せだったのかということに気づかされたのです。
自分は誰かの人生を大きく左右するような仕事に関わっている、苦しんでいる人たちを救うのは自分たちの役割であり、それが仕事なのだと実感しました。
その分プレッシャーは大きく、HSPの私にとって精神的負担はかなり大きかったです。
これまで私は児童相談所の対応が批判されるようなニュースをいくつも目にしてきました。
内情を知っている私からしても、あの対応は良くなかったと思うことはあります。
一方で、児童相談所が誰かを救ったようなポジティブな報道はほとんど見ないとも感じました。
対応を誤りバッシングを受けることは仕方ないと思いますが、みんなが知らないところで多くの問題を解決していることもまた事実なのだと、この仕事を通じて知ることができたのです。
近年は人手不足も深刻化しており、非常に過酷な現場であることは間違いありません。
だからこそ、児童相談所の仕事を通じて誰かを救えたと思うと、自分が誇らしく思えます。
まとめ:児童相談所は「子どもと家庭の最後の砦」
児童相談所は、子どもと家庭を守るための専門機関であり、時には命を守る決断を求められる現場です。
虐待や家庭問題といった重いテーマを扱う一方で、子どもや家庭の変化を間近で感じられるやりがいもあります。
現場のリアルを知ることで、批判だけでなく理解や協力の視点も広がっていくはずです。
また、児相の仕事を正しく理解することは、社会全体で子どもを支えていくためにも欠かせません。
この記事が、児童相談所の役割や現場のリアルを知るきっかけになれば幸いです。
🌱 あなたがHSPであっても、福祉の現場で活躍することは可能です。
自分の特性を理解しながら、自分らしい働き方を探していきましょう。
👉 他の記事では、HSPと福祉職のリアルについても紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。