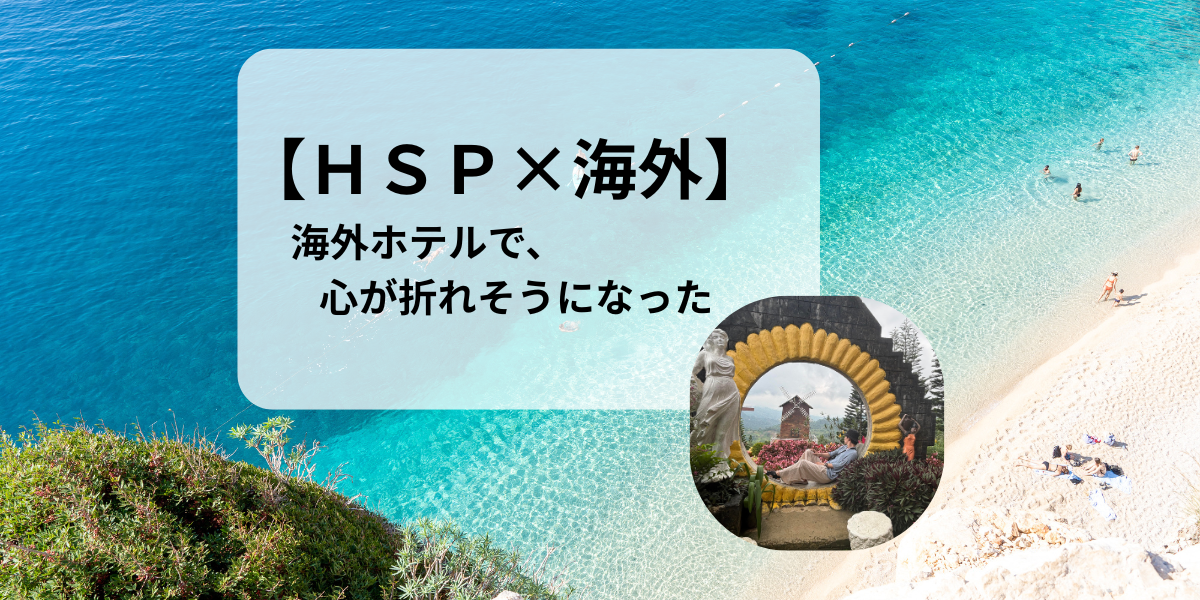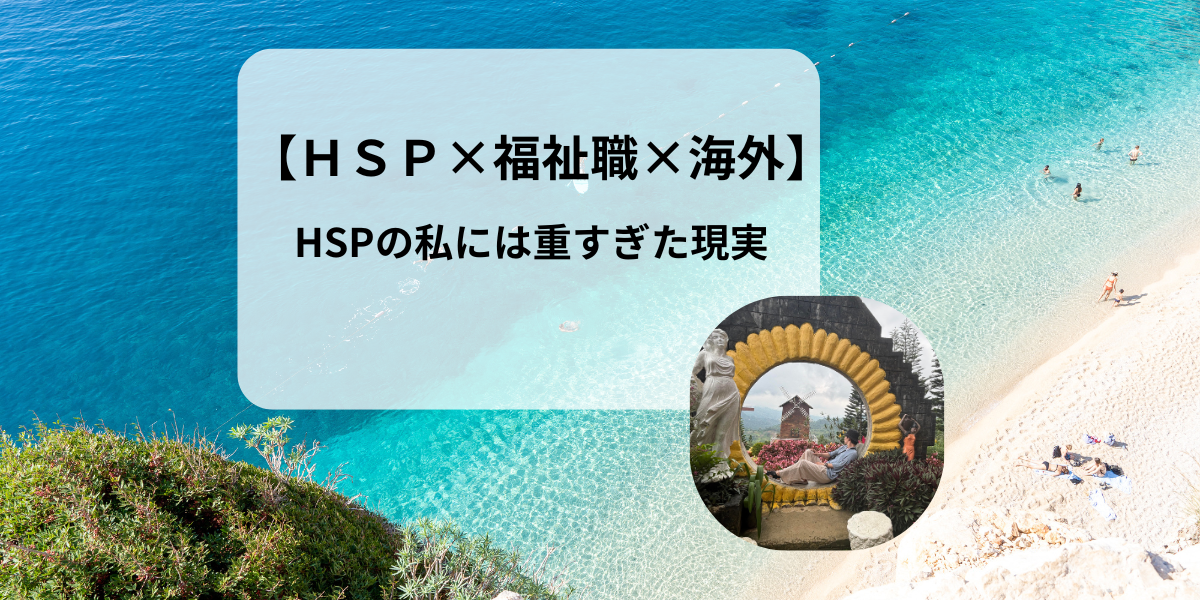【HSP×福祉職】児童相談所での親との関わり

こんにちは、HSP社会福祉士のたくやです。
私は児童相談所で働いていた経験があります。そこでは子どもだけでなく、親御さんと向き合う機会が多くありました。
HSPにとって児童相談所での親対応は特に大きな負担です。ときには強い言葉で責められることもあり、そのたびに心が揺さぶられてしまう自分がいました。
HSPの特性もあり、相手の感情をより深く受け止めてしまい、心身ともに疲れ果てる日も少なくありませんでした。
今回は、私が児童相談所で経験した「親との関わり」の難しさ、そしてHSPだからこそ気づけたこと・工夫できたことについてお話ししたいと思います。
児童相談所で出会う「親」との関わりの難しさ
児童相談所では業務のなかで様々な親と関わることになります。私の場合は虐待指導においてたくさんの親御さんと関わってきました。
指導を真摯に受け止めてくれる場合は良いのですが、正直なところそうでない場合の方が多いと感じました。
児童相談所の対応が気に入らない、虐待を認めない、強い口調で叱責する、物を投げるなど、怖い思いもたくさんしました。
HSPの私はこうした親との対応にひどく疲弊してしまいました。強い口調で責められた日は、感情を深く受け止めてしまい、その日はもう頭からその出来事が離れません。心がひどく消耗してしまうのです。
HSPが児童相談所の親対応で感じやすいしんどさ
そもそも児童相談所の業務は大変なものが多いのです。そこに加えてHSPの方はその気質が故のしんどさを抱えて働くことになります。
相手の怒りや悲しみを深く感じ取ってしまうのは、HSPの抱えるしんどさの一つです。それが自分に向けられたものでなくても、まるで自分に向けられているかのように感じてしまい、疲弊していってしまうのです。
立て続けに親対応が必要な日は、心を回復する暇もありませんでした。意識ここにあらず、といった感じで働いてしまっていた日もあったように思います。
色んな感情を深く読み取り、理解してしまうが故、自分の責任のように思い込みやすいというしんどさもあります。自分がひどく疲弊していることを悟られまいと、表面上を取り繕うことも多かったです。
私もそうでしたが、HSPの方は平気なフリが上手だと思います。その結果周りに頼れず、自分で抱え込み責任を強く感じてしまいます。
私が実践した親対応の工夫(HSPでもできる方法)
刺激に敏感なHSPだからこそ、こうしたしんどさを和らげるための工夫が必要です。
家でリフレッシュする、休憩時間を設けるなどの方法が選べればいいのですが、対応が重なりそうはできない状況がしばしばあります。
今回は、そんな時に私が業務の中で意識していたことを紹介します。
上司への報告
私が最も意識していたのは、上司への報告です。対応の進捗状況や面接の結果、今後の動きなど、とにかく細かく伝えていました。
誰かに話をするだけでも気持ちは軽くなります。それだけでなく、上司と話をすることで、自分の状況を理解してもらえるのです。
私は責任を抱えやすく、周りを頼りづらかったのですが、この報告を介すことで自然とSOSが送れるようになるのです。
責任転嫁するわけではないですが、上司も知っている、その上で私に対応を任せている、そう思うだけで自分だけの責任ではないと思えるようになり、心が軽くなったのです。
言葉や態度の背景を考える
もう一つ、親対応中の工夫として、相手の言葉や態度の背景を考えるように意識していました。
心無い言葉を投げかけられれば、もちろんひどく傷つき疲弊します。ですが、そうした言動は背景にあるはずだと考えるのです。
例えば、一見怒っているように見える親も、本心では虐待を追求されて恐怖しているんだと分析するのです。そうすることで、案外自分の気持ちが軽くなり、余裕ができてきます。
HSPの方であれば、相手の感情を読み取ることに長けていると思うので、ぜひ相手の背景にも目を向ける意識をしてみてほしいです。
HSPの強みが活きた瞬間 ― 親対応から学んだこと
HSPの特性を持っていると、どうしても敏感で疲れやすい方にフォーカスされがちですが、それを上回る強みがあることも学びました。
親と面接しているしていると、相手の小さな変化や感情を察知できます。その結果、相手に適した言葉、共感するような言葉選びができるのです。
初対面の親と関わることも多いですが、相手の気持ちが理解しやすいので、上手に関係性を構築できます。先輩職員に褒められることも多かったですし、褒められた時の嬉しい感情も、HSPであればより深く味わうことができました。
児童相談所の現場だけでなく、人と関わる仕事であればHSPの強みが必ず活きます。HSPの自分を悲観するのではなく、強みに目を向けるべきなのです。


まとめ
HSPにとって、児童相談所での親対応はとにかく大変なものでした。だからこそ、工夫次第で気持ちを軽くすることができること、HSPの強みは必ず活きることを学びました。むしろHSPだからこそできることがあるのです。
繊細である自分を責めてしまうこともあるかもしれません。だけど強みが必ずあること、工夫次第で気持ちが楽になることを忘れないでくださいね。
🌱 繊細さを抱えるあなたへ
少しでも「ラクになれた」と感じてもらえたら嬉しいです。 HSPの感覚を否定せず、工夫とセルフケアでやさしく働けますように。
👉 「自分の繊細さに悩んでいる」そんな方へ
私が心からおすすめできる本をまとめています。きっと気づきや安心が得られると思いますので、よかったら覗いてみてくださいね 。