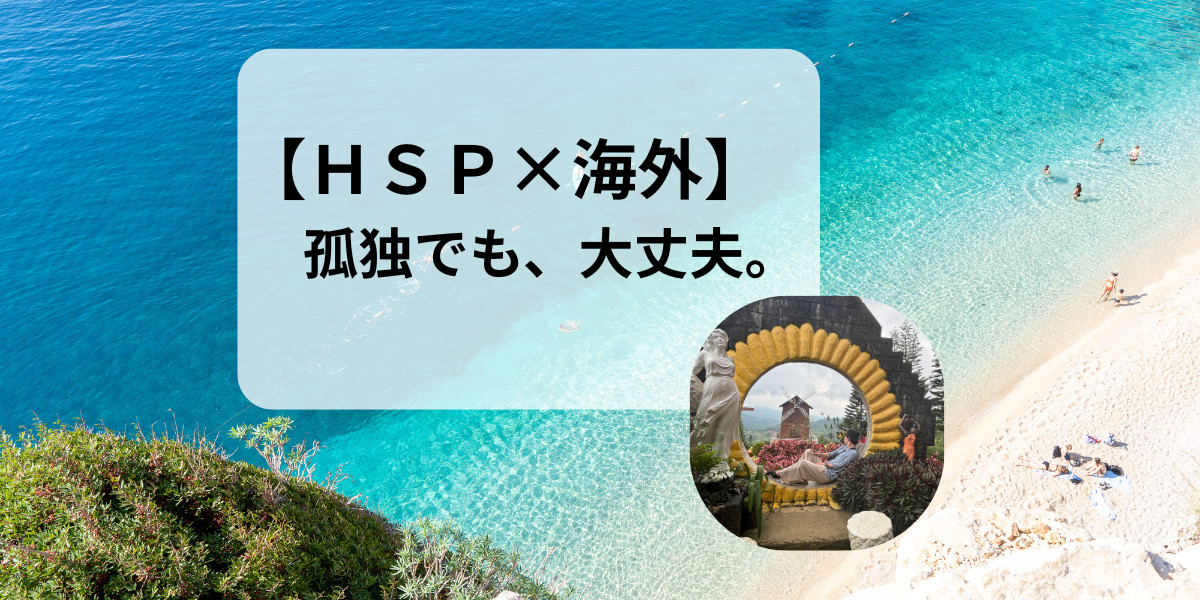【HSP社会福祉士】繊細さを強みに!児童自立支援施設で学んだ対応力

はじめに
「ここはあえて子どもが嫌がることを言おう。」
ある日、施設で子どもと向き合う中で、私がそう思った瞬間がありました。
なぜなら、それがトラブルを未然に防ぐ方法になることもあるからです。
こんにちは、HSP社会福祉士のたくやです。
私は大学卒業後すぐに児童自立支援施設で働き始めました。
そこにはさまざまな事情を抱えた子どもたちが入所しており、
日々の対応は一筋縄ではいきません。
HSPの私は、子どもの表情や声のトーンといった小さなサインに自然と目がいきます。
そこから感情を読み取り、関わり方に活かすことができるのです。
福祉の仕事だけでなく、人と直接関わる仕事や日常生活でもHSPの特性は大いに役立つはずです。
今回は、私のHSP気質が児童自立支援施設の現場で「繊細さを強みに変えた」体験をお話しします。
👉「関連記事:児童自立支援施設で見た、音楽が子どもを支えていた瞬間」

児童自立支援施設での日々
大学卒業後、公務員として児童自立支援施設に配属された私は、想像していた「デスクワーク中心の公務員」とはまるで違う現場に立たされました。
毎日ジャージ姿で子どもたちと生活を共にし、常に彼らを見守り続ける日々。先輩職員から仕事を丁寧に教わる時間も取りづらい、慌ただしい環境でした。
子どもたちのカルテを読み、衝撃を受けたこともよく覚えています。座学で学んでいた福祉の知識とは違い、「こんなことが現実に起きているのか」と胸を打たれました。
そんな特別な事情を抱える子どもたちとコミュニケーションを取る中で、不思議と大きく困ることはありませんでした。我ながら、子どもとのやり取りは得意だったと思います。
HSP気質のおかげで相手の感情を敏感に読み取れる、そして嫌われることを避けようと自然に立ち回れる、さらに「仕事だから頑張らなければ」というプレッシャー…。複雑な感情を抱えつつも、子どもたちとの関係を築いていきました。
HSP気質がトラブル回避に役立った場面
人と関わる仕事では、繊細さが役立つ瞬間が数え切れないほどあります。子どもが不穏になる、喧嘩が始まりそう、ずるをしそう…HSP気質の人なら分かると思うのですが、「なんとなく察知できてしまう」ものです。
あるとき、特に手のかかる子どもが何人も同時に入所しており、施設内はトラブル続きでした。子ども同士の一触即発の喧嘩を前に、私はあえて「子どもが嫌がること」を言いました。その瞬間、怒りの矛先は私に向かいましたが、大きな衝突は避けられたのです。
日々の関わりの中で、子どもが「今言われて嫌なこと」「逆に嬉しいこと」が自然と分かるようになっていました。
トラブルを回避するために、あえて自分に怒りを引き受ける。課題から逃げようとする子に、あえて痛いところを突いて向き合わせる。もちろん人格を否定する発言は絶対にせず、その後のフォローも丁寧に行いました。
HSP気質だからこそできた「察知」と「選択」。繊細さは決して弱さではなく、現場で大きな力になるのだと感じました。
後から振り返ると、冷静な判断というより「感覚的な判断」だったと思います。
繊細さを強みにできた理由
当時の私は、自分の特性を「みんな同じようにできるもの」と思い込んでいました。しかし先輩や同僚と話すうちに、それが私特有の強みであると気づいたのです。
トラブルを未然に防いだり、子どもや職員から相談を受けたりすると「ありがとう」と言われることが増えました。もちろん苦手な業務もありましたが、互いに助け合いながら何とか3年間働き続けることができました。
「繊細さが強みになる」──それを実感できたのは、間違いなくHSP気質のおかげでした。
👉 「関連記事:児童自立支援施設で出会った『気持ちが分からない』子どもの成長物語」

まとめ:HSPの繊細さは武器になる
ここまで読んでくださりありがとうございます。HSPは「繊細で疲れやすい」といったマイナス面が注目されがちですが、それ以上に強みもたくさんあります。
冒頭で紹介したように、福祉の現場ではHSP気質が子どもとの関わりやトラブル回避に大きな力を発揮しました。これは福祉だけでなく、日常生活やほかの仕事でも必ず活きるものだと思います。
どうか、自分の気質を否定せず、強みとして活かす視点も持ってみてください。少しでも誰かの参考になれば嬉しいです。
👉 「自分の繊細さに悩んでいる」そんな方へ。私が心からおすすめできる本をまとめています。きっと気づきや安心が得られると思いますので、よかったら覗いてみてくださいね 。