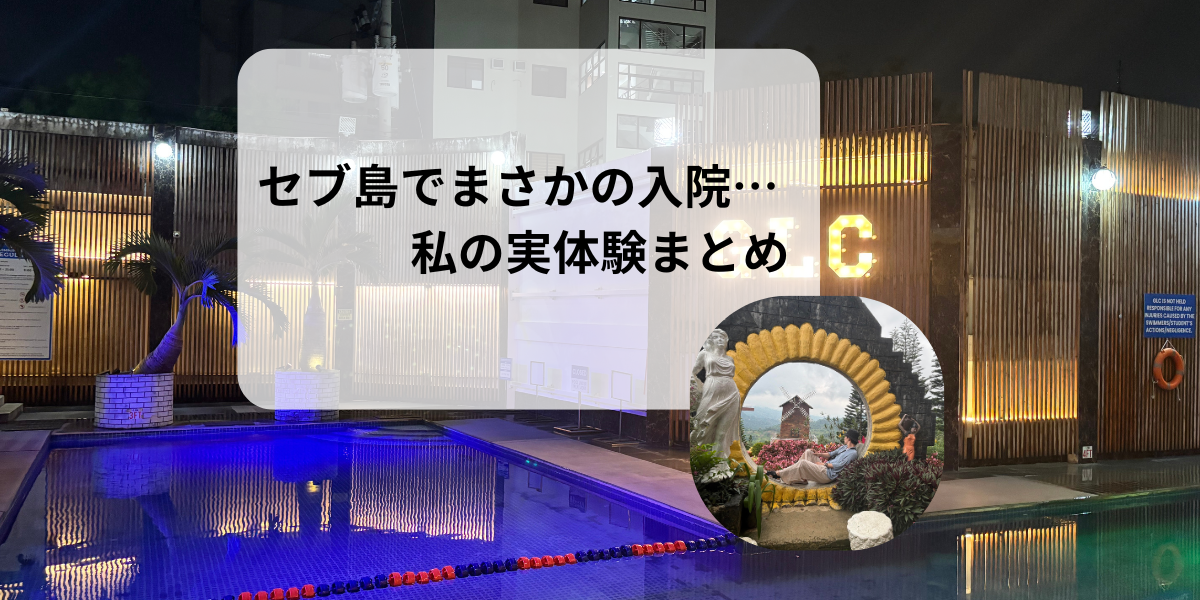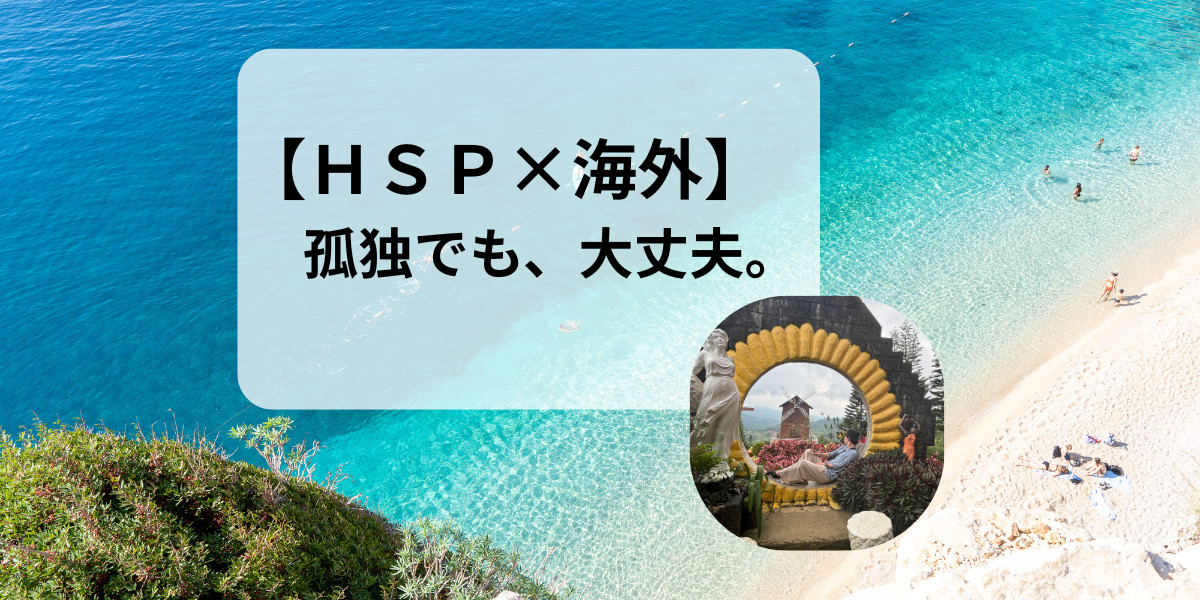【HSP×福祉職】電話対応がつらかった日々

「プルルル…」
着信音が鳴った瞬間、心臓がぎゅっと縮こまり、体がこわばります。
こんにちは、HSP社会福祉士のたくやです。
私は福祉の現場で働く中で、電話対応がとても苦手でした。
特に児童相談所では、いつ、誰から、どんな内容の電話がかかってくるかわかりません。
HSP気質の人にとっては、その「予測できない状況」や「相手の感情に敏感に反応してしまう特性」が大きなストレスになります。
この記事では、私がHSPとして福祉の現場で経験した電話対応の苦しさと、心を守るために実践した工夫をお話しします。
👉 「関連記事:児童相談所とは?役割と現場で働く人の実際」

HSPが電話対応をつらく感じる3つの理由
1.電話の着信音がプレッシャーになる
児童相談所では、昼夜問わず電話が鳴ります。
着信音が鳴るたび、心臓がぎゅっと縮み、身体が反射的にこわばります。
「もしあの保護者だったら…」「緊急案件だったら…」と頭をよぎるだけで、心拍数が上がってしまうのです。
それでも周囲の目を気にして電話を取る——その繰り返しで、少しずつ心は削られていきました。
2. 相手の声や感情を吸収してしまう
電話口では、保護者から罵声を浴びせられることも、関係機関から小言を言われることもよくあります。
声のトーン、息づかい、間の取り方…HSPはそういった感情の揺れを敏感に察知し、無意識に心に溜め込んでしまいます。
そのため、電話が終わっても頭の中で会話を何度も再生し、感情を引きずってしまうのです。
3.電話は一発勝負でやり直せない
電話は録音しない限り、その場で正確に聞き取る必要があります。
メモが追いつかないと「間違えたらどうしよう」というプレッシャーが増大しますね。
何度も聞き返すことへの遠慮もあり、電話中は常に緊張しっぱなしでした。
実際にあった電話対応のエピソード
激しい罵声が1時間続いた日
ある日、虐待通報を受けて保護者に連絡したところ、来所要請に激しく反発されました。
「ふざけんな!」「なんで私が!」と、1時間近く怒鳴られ続けましたね。
所での面談でも同じように怒鳴られましたが、最後はなぜか機嫌が良くなり帰っていきました。
「話を聞いてほしかったのかもしれない」と思う一方で、HSPの私にとってはただただ消耗する時間でしたね。
電話を切ったあと、しばらく席を立つことができず、ただぼんやりと受話器を見つめていました。
心身の限界で療養休暇へ
電話対応だけでなく業務全体の負荷も限界に達し、療養休暇を取得したこともありました。
周囲から見れば、まだ働けているように見えたかもしれません。
吐き気・食欲不振・脱水状態…それでも「休んではいけない」と思い込んでいました。
休職後、復帰時には上司が業務を見直し、電話対応を免除してくれました。
その経験から、「助けを求めることは弱さではない」と気づくことができました。
HSPでもできる電話対応の工夫
「出る電話」をあらかじめ決める
- 例:「3回に1回だけ取る」「2回連続では取らない」
- 出る・出ないの判断で迷う時間が減り、心の負担が軽くなります。
メモ用テンプレートを作っておく
- 名前・日時・要件・対応内容をあらかじめ書けるフォーマットを準備しておくと安心。
終わったら気持ちを切り替える儀式を持つ
- 深呼吸、ストレッチ、席を立って水を飲むなど、電話後にリセットする習慣を作る。
👉 「自分の繊細さに悩んでいる」そんな方へ
私が心からおすすめできる本をまとめています。きっと気づきや安心が得られると思いますので、よかったら覗いてみてくださいね 。

まとめ:助けを求めてもいい
HSPは感受性が高く、人の気持ちを汲み取ることができる貴重な存在です。
でも、その力は自分をすり減らしてまで使う必要はありません。
「助けを求めること」は弱さではなく、自分を守るための大切な行動です。
電話対応がつらいなら、あなたの心と体を守る方法を探してほしい。
この記事が、同じように悩む方の一歩につながれば嬉しいです。
👉 「関連記事:職員同士の口論に巻き込まれるしんどさ」